「雪の日に」 校長 古賀誠子

1月10日、金曜日の早朝、前日の夜から雪が降り積もり、西鉄バス、スクールバスなど、交通機関が遮断され、休校になった日がありました。車で通勤するのは、危険だと思いましたので、学校まで歩くことにしました。年に1~2回、こういう日があるので、長靴と手袋、マフラーなどの防寒具は揃えてあります。今年も、活躍するなと思いながら、雪の日グッズを身に着け、朝、6:40に出発しました。歩くと、いつもとは違ういろんな景色が見えてきます。まず、真っ白になった道路、車もほとんど走っていないので、人が歩く音がいつも以上によく聞こえます。雪道が、お日様に照らされて、美しいと思ったとき、思わずスマホで、シャッターを切ってしまいました。顔に当たる空気が、冷たく、足先もかじかんでいるけれど、いつもとは違う景色や冷たい空気が新鮮で、ウキウキしました。
こんな日は、不思議なことが起こります。知らない人が、どんどん話しかけてくるし、私も話しかけたくなる。「あら帽子をかぶると違うわよ、頭が寒そう。」とか、「そこ滑りやすいから気を付けて」とか、バス停の近くを歩くと、「一応バス停まで来てみたけど、走っているはずないわよね」とか、「バスは期待できないから、なんとか高宮まで歩いていくわ」とか。途中で、車がスリップして、立ち往生している車を、通りがかりの人たちが、数人で押している姿も見ました。以前、本校で勤務されていた先生にも偶然出会い、懐かしく思い、立ち話してしまいました。寒くて、不便に感じた1月10日という一日を、いろんな形で、隣人と分かち合うことで、随分気分が軽くなった。人と人がつながるということは、意外と身近にあって、こうやって関わることによって、人から元気をもらっているのかもしれないと感じました。寒い雪の日の朝、学校に来るのに、1時間以上かかりましたが、到着した時には、すがすがしい気分でした。
さて、報道などですでに知っていると思いますが、今から30年前、1月17日5時46分、兵庫県の淡路島北部沖の明石海峡を震源として、マグニチュード7.3の地震が発生しました。近畿圏が大きな被害を受けました。「阪神淡路大震災」です。特に震源に近い神戸市の市街地の被害は甚大で、近代都市での災害として、日本国内のみならず、世界中に大きな衝撃を与えました。世界中から捜索のための人的支援をたくさん受けながらも、犠牲者は6434人にも達し、第二次世界大戦後に発生した自然災害では、東日本大震災が発生するまでは最悪のものであったと言われています。
福岡県でも被災した生徒たちを、積極的に学校で受け入れるようにとの政府からの要請があり、福岡県全体でも多くの被災した学生たちを受け入れたそうです。福岡県のある高校での話です。被災した男子1名を受け入れました。文化祭の弁論大会で、震災の経験を語りたいと本人から申し出があり、全校生徒の前で震災の様子を語ってくれました。記憶から消すことができないほどの苦しい経験をした人がその経験を口に出して人と分かち合うことは、想像を絶するエネルギーと苦痛が伴うと言われます。それなので、校長先生が何度も彼の意志を確認しましたが、彼の決心は揺らぎませんでした。倒壊した家の中で、たんすに挟まれた父親の足がどうしても抜けず、家族が逃げ出せずにいた。父親が「この足を切り落としてくれ」と何度もその生徒に頼んだそうです。「父親を救いたい」という気持ちと、「父の足を切り落とすことなんて自分にはできない」と言う気持ちが葛藤したそうです。そして、やはりそれができないと分かった時、父親が「自分はもういいから、母さんと早く逃げろ。そして私の分まで生きてくれ」と言ったそうです。すでに激しい火災が同時に起こり、それが父親の最後の姿であったという話です。この話を聞いていた全校生徒、そして本人も、声をあげて泣きました。
さて、神戸の小中学校では、震災以来、歌われてきた歌があります。『しあわせを運べるように』という歌です。ひょっとしたら、小・中学校で習ったことがある人がいるかもしれません。今年の成人式、神戸では、成人代表の方たちの提案で、この歌を作った人が指揮者をつとめ、約8、800人の成人が、この歌を大合唱しました。テレビでそれが報道されているのを見て、みなさんと分かち合いたいと思いました。
震災が起こった直後、この歌で日本全体がつながり、神戸の人たちと心を合わせ、全国の人々が、震災と向き合いました。今でも、神戸ではこの歌を知らない人はいないと言われていますが、神戸の復興を願い、皆で支援しようと作られたこの歌、当時、神戸市内の小学校で教員であった、臼井真さんという方によって、作られたそうです。ご自身も被災され、東灘区の自宅は全壊。震災から約2週間後、身を寄せていた親戚宅で、生まれ育った街の変わり果てた姿を見て、大きな衝撃を受け、わずか10分で、この歌を作ったそうです。ボロボロに傷ついた自分のふるさとを目の当たりにしながらも、「わたしたちは決して負けない」という強い決意がこの歌から伝わってきます。
この曲は、そのあと多くの人々の心を捉え、希望の灯となって、災害からの復興を願うシンボル曲になりました。神戸では、今でも市内の小・中学校をはじめ、さまざまな式典で、大切に歌い継がれています。そして、その後に続いた、福岡西方沖地震、新潟中越沖地震、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震でも、神戸から被災地にこの歌が届けられたといいます。今では、英語、中国語、フランス語、イタリア語、韓国語などいろんな言語に訳されて、世界の国々でも歌われています。手話も交えて子どもたちが心を込めて歌っている姿が印象的です、どうぞご覧ください。
復興のシンボル曲『しあわせ運べるように』~神戸から東日本、日本各地、世界へ~
今年、1月16日、阪神淡路大震災追悼の広場で、「よりそう」と言う文字がろうそくの明かりでつくられていました。「命の輝き」を意味するろうそくの明かり、その一つ一つがつながって、「よりそう」という文字となり、それを人々が囲んで、亡くなった方々に祈りが捧げられていました。亡くなった方々、ご遺族の方々、被災されたすべての方々のうえに、神様の慰めと守り、導きがありますように。
最後に、片柳神父様の著書より、『つながって輝く』をご紹介します。「山奥に住む部族の長が、街にやってきて、生まれて初めて電球を見た。まばゆく輝いて、夜の闇を照らす電球の力に感動した彼は、街の電気屋で電球をたくさん買って帰った。ところが、それらの電球は、彼の村ではかがやくことがなかった。なぜなら、彼の村にはまだ電気が通っていなかったのだ。人間も電球のようなものだと思う。どれだけ大きな力を秘めた電球も、電気なしでは決して輝くことができないのとおなじように、どれだけ大きな力を秘めた人間も、自分だけでは決して輝くことができない。勉強して資格をとったり、お金を稼いで着飾ったりしても、人間は決して自分だけでは輝くことができないのだ。人間を輝かせるために必要な電気、それは人と人とがつながるとき、そこに生まれる愛だと思う。―中略― 人間の不幸の多くは、最初に紹介した部族の長のように、電球がそれ自体として輝くことができると思い込むことから生まれるように思う。自分のことだけを考え、自分を磨き、自分を飾り立てることばかりに夢中になっている限り、わたしたちは自分の命を輝かせることはできない。自分のことばかりを考えるのをやめ、周りの人に心をひらいたとき、家族や友人、そして神様との間にしっかり絆を結んだとき、わたしたちの心に愛という電気が流れる。そのとき、わたしたちの命は、まばゆく輝き、辺りを照らし始めるのだ。思いあがって、つながりを絶つことがないようにしたい。」
人と人とを結ぶ絆の中で、生かされている私たちです。そして、その根底には愛という電気が流れています。まずは、身近なところにある、自分と他者との繋がりに心を開き、育てていくことから始めてみましょう。
今日もよい一日をお過ごしください。
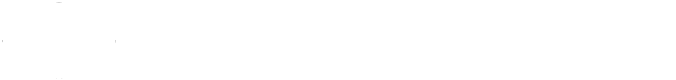
 採用情報
採用情報 福岡海星女子学院
福岡海星女子学院